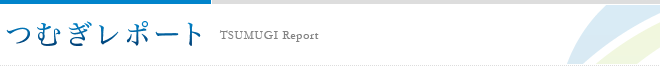No.0132014.06.16
生前贈与が相続時におよぼす影響
平成27年から相続税が増税されることが決まり、相続の対策として生前贈与が注目されています。今回は、生前贈与が相続税および遺留分の計算に与える影響についてご説明します。
生前贈与財産に相続税が課税される場合
親が子供に生前贈与した財産は、原則として親に相続が発生しても相続税の対象にはなりません。しかし、以下①②の贈与は、親が亡くなった際の相続税の対象にもなりますので注意が必要です。
①相続時精算課税(※1)、非上場株式や農地の納税猶予制度(※2)を選択した贈与
(※1)相続時精算課税とは、65才以上(H27年より60才以上)の親から20才以上の子(H27より孫も含みます)に対して行う贈与に選択できる制度です。当該制度を選択すると2,500万円(選択時からの通算)を超えた場合に、超えた金額に対して20%の贈与税を納税します。そして、相続発生時に当該贈与財産を相続財産に加算(贈与時の評価額で計算)し、既納付の贈与税額は相続税から控除して相続税を計算します。
(※2)相続財産に組み込まれて計算された相続税は、一定の要件のもとで納税猶予することができます。
② 相続(遺贈を含む)により財産を取得した者に対して、相続前3年内になされた贈与
相続前3年内に贈与された財産は、贈与時の評価額で相続財産に加えて相続税が課されます(当該贈与に対する贈与税は相続税から控除されます)。なお、相続により財産を取得しない孫等に対する贈与であれば、たとえ3年以内の贈与であっても相続財産に組み込まれることはありません。そのため相続の発生が近いと予想される場合、相続により財産を取得する予定の子よりも、孫等への贈与の方が一般的に税負担が少なくなります。ただし、(イ)住宅取得資金贈与により贈与税の課税価額に算入されなかった金額、(ロ)婚姻期間が20年以上である配偶者に対する贈与の特例により課税されない部分(最大2千万円)の金額、(ハ)教育資金贈与により非課税とされた金額については、たとえ相続により財産を取得する者への3年以内贈与であっても相続税の対象になりません。したがって、これらの制度を活用した贈与は相続直前であっても相続税の対象となる財産を減らすことに有効です。
遺留分の対象となる生前贈与
税金の話とは異なりますが、遺留分対策で贈与を行う方がいます。しかし、遺留分の対象になるのは相続時点で被相続人が所有している財産だけではありません。生前に贈与した一定の財産も遺留分の対象になります。具体的には、①相続発生前1年以内になされた贈与、②遺留分を害することを知ってなされた贈与、③特別受益も遺留分の対象になります。ですから、相続の直前(1年以内)の贈与により相続財産を減らしても遺留分は減少しません。また1年より前の贈与であっても、贈与者の年齢・健康状態・収入・全財産に占める贈与財産の割合・贈与時期を勘案して遺留分を害する贈与と認められる場合や、特別受益(共同相続人に対する同族会社の株式・不動産・開業資金・多額の教育資金等の贈与、相続人を著しく不公平にする生命保険等)は遺留分の対象になります。相続人でない孫等への贈与は特別受益になりません。ただし孫への贈与であっても実質的に子への贈与とみなされる場合には特別受益に該当しますので、注意して下さい。
また遺留分は相続時の時価で計算されます。贈与時において100万円だった自社株が、相続時に3億になっていたら、3億円で遺留分が計算されます。子供が頑張って会社を大きくしても遺留分も同時に大きくなります。これを解決する方法として固定合意・除外合意という制度がありますが、法的に不安定で活用が難しいところです。なお、遺留分の減殺請求は相続を知ってから1年以内(知らなかった場合でも相続開始後10年以内)にしなければなりません。また減殺請求があった場合に減殺される順序は、①遺贈(遺贈の中の減殺の順序は遺言書で指定することができます)、②死因贈与、③贈与(後の贈与から減殺)となります。これらも考慮して生前贈与を検討することが実務上は大切です。
[ 担当:笹島 修平 ]
このレポートのPDF
tsumugi_report013.pdf03-6910-2575お気軽にお問い合わせください
- 住所
- 〒105-6405
東京都港区虎ノ門1-17-1
虎ノ門ヒルズビジネスタワー5階
アクセスマップ - 最寄り駅
- 日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩1分
銀座線 虎ノ門駅 地下通路にて直結
千代田線・丸ノ内線・日比谷線 霞ヶ関駅 徒歩約6分
都営三田線 内幸町駅 徒歩約7分
JR 新橋駅 徒歩約10分